企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
現場力
2018年8月号
満たされぬものを懸命に育てていく努力が人間を鍛えぬく
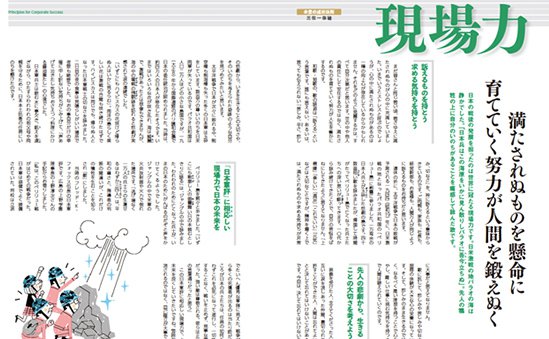
日本の戦後の発展を担ったのは世界に冠たる現場力です。日米激戦の地パラオの海は静かでした。
「日本兵はこの海原をいかに見ん散りしパラオに吾れ今ま立ちぬ」。先人の犠牲の上に自分のいのちがあることを痛感して詠んだ歌です。
訴えるものを持とう求める気持ちを持とう
まだ皆さんと同じ若い頃、若さゆえに満たされぬものが心の中に充満していました。
いまでいうとストレスと呼ぶのでしょうが、心の中に満たされぬものがあるのは一種の向上心が存在しているからかもしれません。
それをどのように発露するかは、すべて自分次第だと思います。世の中や他人の責任にして安住するのではなく、満たされぬものを育てていく努力が人生を豊かにするのです。
和歌・短歌の、歌の語源は「訴える」という言葉です。誰にも言えない、あるいは、言っても伝えられない「苦しみ、辛さ、悲しみ、切なさ」を、
神に訴えるという意味からきているのです。ご両親も、家族も、社長も、経営幹部も、お客様も、人間万人が同じように訴えるものをお持ちだと思います。
連休の折に、太平洋戦争で日本の敗戦が予測される1944(昭和19年)に、日米激戦の地となったパラオ共和国の「ペリリュー島」に慰霊に参りました。
1万有余の日本人兵士が玉砕した悲劇の島です。四十数首拙い歌を詠みましたが、帰国して時間がたってペリリュー島で亡くなった兵士たちへの深い思いが蘇ってきます。
10代から詠み続けてきたことで、自分の苦悩をばねにしてきたように思えてなりません。「上機嫌」「楽しい」「満足」「これでいい」「元気」などは大切なことですが、
精神を磨く上では、満たされぬものや求める気持ちが非常に大事だと思えてなりません。
歌に託して、悲しみや苦しみや切なさや屈辱の体験が大きな心の栄養になっています。そして、悲しみのまま生きるのではなく、
なるべく高い理想を持つことで心を燃やし、難しい仕事に挑む気持ちを持つことで人間は鍛えられていくのです。
先人の悲劇から、生きることの大切さを考えよう
恩義を受けた人、支えてくださった人、お互いに涙を流しあった仲間、裏切られても許すことができた人、
人間は忘れてよいことと決して忘れてはいけないことがあるのです。今回は、決して忘れてはいけない先人の悲劇から、
いまを生きることの大切さや、そのいのちを与えられた奇跡のような自分を見つてみたいと思います。
本記事は、月刊『理念と経営』2018年8月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






