企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
社長力
2025年11月号
よく学び、よく聞き、良く思う
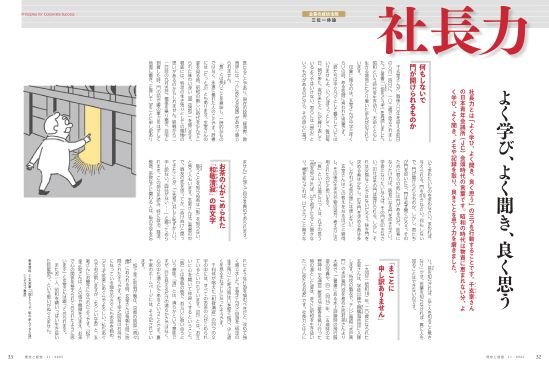
社長力とは「よく学び、よく聞き、良く思う」の三つを行動することです。千玄室さんの日本青年会議所(JC)会頭時代の言葉です。昭和の時代は物資に恵まれない分、よく学び、よく聞き、メモや記録を取り、良きことを思う力を磨きました。
何もしないで門が開けられるものか
千玄室さんが、戦後八〇年を迎える前日の八月一四日に、一〇二歳で逝去されました。ご著書『一盌をどうぞ』を再読しました。昭和という時代を生き切り、天命とともに生きる境地にたどり着いた歩みが記されています。
印象に残るのは、玄室さんが中学三年くらいの時、ある牧師に言われた言葉です。
「君たちは平々凡々として暮らしていてはいけませんよ。いつもぼうっとして、毎日毎日、朝が来た、夜が来たと、ただ繰り返しているようではいけない。君らには『良心』というものがあるのだから、その良心に基づいて求めたいものを求めなさい。
求めれば、与えられる。門を叩きなさい。何もしないで、門が開けられるものか。しかし、君たちが門を叩いたら、門は必ず開くだろう。そのために君らの前には門があるのだ。医者になりたければ、医者になる門を叩きなさい。学者になりたいならば、その門を叩きなさい。
叩けばその門は開けられる。しかし、それは安易なことではないだろう。狭き門を求める者は少なし。広き門を求める者は多し。しかれども命の泉には達しない」
玄室さんはこの教えをなるほどと納得し、その後の生き方や物の見方、考え方に活用されたのだと思います。
「長」という立場に立つ人は、孔子の言う「命を知らざれば、以て君子たること無きなり。礼を知らざれば、以て立つこと無きなり。言を知らざれば、以て人を知ること無きなり」です。言葉を知らなければ、真に人を知ることはできないのです。
「まことに申し訳ありません」
一九四三(昭和18)年、二〇歳になられた玄室さんは、学徒出陣で舞鶴海兵団に入隊します。特攻の戦友で、テレビ番組『水戸黄門』の水戸黄門役を務めた西村晃さんより大柄で、ご著書にある水上訓練時の飛行服姿の写真や、
四一(同16)年、一五歳時の北野神社(天満宮)献茶式で献香を執り行った時の凛とした姿は、まさに昭和を生き抜いた「人に長たるお姿」です。社長力とは人に長たることであり、現在の政界、経済界、教育界には、「人に長たる気風」があまり感じられません。
「長」とは長いことを意味し、一時的なものではなく、永遠に優れた人のことです。辞書には「たっとぶ」ともあります。玄室さんの姿を見る時、昭和の厳しい時代を歩んでこられた味わい深い「道(境地)」を感じます。
根底には、特攻の生き残りとしての懺悔の思いがあるのかもしれません。終戦から二一日目の九月五日、電車を乗り継ぎ、自宅に到着した時、門の前で腰の軍刀をはずして地面に置き、正座して「まことに申し訳ありません」と強くご自分を責めておられます。
本記事は、月刊『理念と経営』2025年11月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






