企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
管理力
2025年8月号
インドの未来に希望を託した鈴木修氏
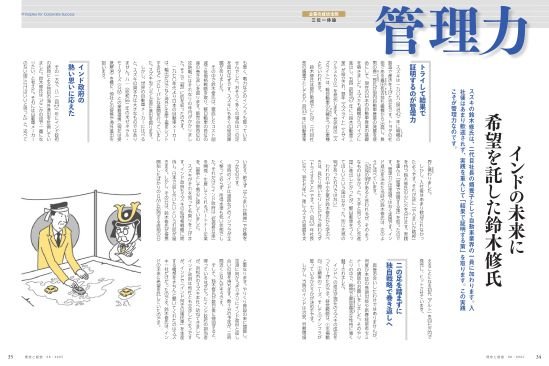
スズキの鈴木修氏は、二代目社長の婿養子として自動車業界の一員に加わります。入社後はあまり歓迎されず、実践を重んじて「結果で証明する策」を取ります。この実践こそが管理力なのです。
トライして結果で証明するのが管理力
スズキは一九〇九(明治42)年に織機の製造で産声を上げた会社です。トヨタの社祖である豊田佐吉翁も織機から出発し、長男の喜一郎氏が国内自動車産業の発展を使命にして、現在の日本の自動車産業の基礎を築きました。スズキも織機からバイクに進出し、五四(昭和29)年に「鈴木自動車工業」が設立され、翌年「スズライト」(2サイクル360㏄)を発売します。発売時の「スズライト」は、軽自動車の先鞭をつけた車種ともいわれます。
鈴木修氏は銀行勤務でしたが、二代目社長の婿養子として五八(同33)年に自動車業界に携わりました。
しかし、入社後はあまり歓迎されなかったようです。それが逆に「やらまいか精神」を持つ鈴木修氏の心に火を点けます。実践を重んじ「結果で証明する策」を取ったのです。管理力とは理論ではなく実践です。インド進出を決めた当時の鈴木修氏は、次のように述べています。
「先見の明があると言われるが、そのようなものはなかった。大手と同じように先進国に進出したかったが、軽自動車をつくってほしいという国はなかった。別に先見の明があったわけではない」
われわれ中小企業が鈴木修氏から学ぶべきは、見たり聞いたりしただけで終わらず「トライすること」です。七八(同53)年社長になり、翌七九年に、後にスズキの発展を支えることになる初代「アルト」を四七万円で発売し、ヒットさせています。
二の足を踏まずに独自戦略で巻き返しへ
直接お会いしたわけではありませんが、何度か本誌の巻頭対談や新春経営者セミナーの講師のお願いをしました。そのやりとりの中で、緻密で豪放磊落な性格に強く魅了されました。
インドへの進出が現在のスズキの成功をつくり上げたのです。経営戦略は、①市場動向、②顧客のニーズ、そして③インフラが整っているかどうかが決め手です。
しかし、当時のインドは治安、労働環境も悪く、電力などのインフラも整っていませんでした。おそらく多くの場合は二の足を踏むはずです。スズキにも多くの経営課題がありました。
その中で鈴木修氏は、徹底したコスト削減で低価格戦略を取り、軽自動車の首位の座の巻き返しを図ります。販売台数首位の攻防戦にはそれなりの年月がかかりました。そこで「軽」に的を絞ったのです。
一九七〇年代より日本の自動車メーカーは、輸出だけでなく海外に生産工場をシフトするなど、グローバルな展開を行っていました。スズキもアジア方面に進出を図ります。
しかし、世界の自動車メーカーに比べると、スズキの資本力は大きなものではありません。八一(昭和56)年の米ゼネラル・モーターズ(GM)との業務提携(現在は提携解消)を機に、他社との提携で海外進出を狙います。
本記事は、月刊『理念と経営』2025年8月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






