企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
管理力
2025年3月号
トップマネジメントの存在理由
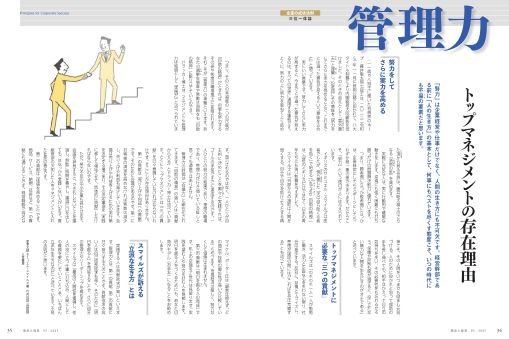
「努力」は企業経営や仕事だけでなく、人間の生き方にも不可欠です。経営幹部である前に「人の生き方」の基本として、何事にもベストを尽くす態度こそ、いつの時代にも不易の要素だと思います。
努力をしてさらに実力を高める
二一歳で八冠王に輝いた将棋界のホープ・藤井聡太現七冠王は、二〇二三(令和5)年一一月に首相公邸に招かれて、八大タイトル制覇により内閣総理大臣顕彰を受けました。そのときの返礼として「雲外蒼天」と揮毫し、記者団にその意味を「努力をしてさらに実力を高めることで、これまでとは違った景色が見えるという意味を込めた」と語っています。
実にいい言葉です。努力してさらに実力が高まると、今までとは違った景色が見えるのは、すべての世界に通用する事柄です。とくに、努力の上に努力を重ねて上り詰めた頂から見る世界は、藤井聡太棋士のさらなる「浩然の気」を高めます。
実際に元気な人は、実に行動的で機敏な動きをします。逆境にも強く困難にも打ち勝つだけの問題解決能力に優れています。
つまり、勝者側に立つか敗者側に立つかは、企業経営にしてもスポーツにしても、わずか紙一重の差で決まります。だからこそ、「努力」という徳目が人には与えられています。
イギリスのサミュエル・スマイルズは医者でしたが、傍ら著した「天は自ら助くる者を助く」で始まる『Self-Help (自助の精神)』は、当時のイギリスだけではなく、日本の青年たちにも強い影響を与えました。
スマイルズは「外部からの援助は人間を弱くする。自分で自分を助けようとする精神こそ、その人間をいつまでも励まし元気づける。人のために良かれと思って援助の手を差し伸べても、相手はかえって自立の気持ちを失い、その必要性をも忘れるだろう。保護や抑制も度が過ぎると、役に立たない無力な人間を生みだすのがオチである」と述べています。
トップマネジメントに必要な「三つの貢献」
スマイルズは「われわれ一人一人が勤勉に働き、活力と正直な心を失わない限り、社会は進歩する。反対に、怠惰とエゴイズム、悪徳が国民の間にはびこれば社会は荒廃する」とも述べています。
つまり、その人の幸福度の一つの尺度が「自助の精神」だとすれば、何事も努力するその姿や態度は職場風土に拡散されます。それこそが「管理力」の神髄といえます。あなたの真摯な態度や言動は周囲をも「自助の精神」に駆り立てていくのです。
ドラッカー博士は、マネジメントや管理力は結論として「実践だ」と述べられています。指示されるのではなく、一人ひとりが自主的に決めたことを粛々と実践すれば、ゴールの手前ですでに達成するのです。一人ひとりの努力の結果であり、理想の職場であり、管理力が行き届いている証しと言っても過言ではありません。
管理力の評価は「会議力」に顕在化されてきます。「自助の精神」の強い人は「貢献から入る」とドラッカー博士は述べています。とくにトップマネジメントは「三つの貢献」を日々意識していなければならないわけです。そこにしか存在理由はありません。
第一の貢献は「売り上げや利益への貢献」です。そのために会議があるのです。第一にお客様の満足を高めなければ客数は減少し、売り上げや利益も減少していきます。会議は売り上げや利益を上げるための実行策を決定する場であり、その決定事項を「実践に移して達成させて、具体的に貢献」しなければならないのです。
ただ、努力不足の中小企業も見かけます。会議を拝見すると、できもしないことを議論し、無駄に時間を費やし、議論に口を出しても、はなっから実践しない人がいます。貢献意欲の欠如した人をマネジメントに入れた社長の責任です。
第二の貢献は「価値を高めること」です。商品、サービス、納期、技術など、第一の貢献にも通じることです。経営戦略で有名なマイケル・ポーター氏は「顧客は絶えず、どの商品や技術の優位性が高いか比較している」と述べます。市場経済は厳しく、努力なくして価値は生まれません。
第三の貢献は「明日を創る人の育成」です。机上の空論をZ世代は見破ります。実践を望む人や努力を好む人を信頼します。明日を創る人をつくるためにも、あなた自身がモデル(お手本)になることをお勧めします。
本記事は、月刊『理念と経営』2025年3月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






