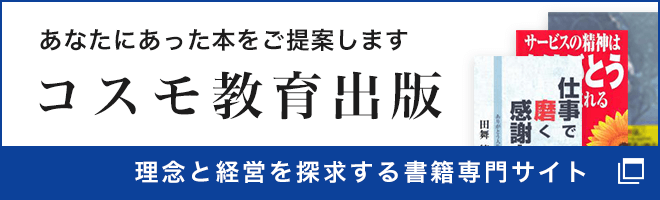企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
管理力
2020年11月号
イノベーションは「素直な心」から生まれる

「ハーバード・ビジネス・レビュー」誌が発表した「セルフ・アウェアネス」(自己認識・自己への気づき)は、これからの経営幹部に欠かせない能力です。正しい自己認識や自己への正しい気づきがイノベーションに大きく影響します。
正しい自己認識がイノベーションを生む
私どもの「経営理念と戦略ワンポイント講座」では、P・F・ドラッカー博士が主張している二つの重要な企業経営の機能を紹介しています。マーケティングとイノベーションの働きであり、経営幹部のアフターコ
ロナに欠かせないマネジメントの根幹です。
日本企業は一部を除いて、一時、世界ナンバーワンを誇ったさまざまな製品や技術で世界に敗れています。大きな理由は世界の潮流であるイノベーションで世界に遅れたことです。もちろん、立派な企業は残っています。その一つである浜松ホトニクス㈱は、「光電子増倍菅」などで世界シェアを九〇㌫近く持つ企業です。
晝馬輝夫さんは三人で起こした創業間もない頃の中小企業時代、現場でゼロからの技術に挑み、経理にも取り組み、品質を重視する欧米市場への営業でも苦労されました。当時の創業社長を補佐するために、ないない尽くしだからこそ、自ら学び多様な経営スキルを身に付けるしかなかったのです。その点、今の中小企業はまだ管理力という面で甘さがあるように思います。
ニュートリノ(中性微子)の研究でノーベル賞を二〇〇二(平成14)年に受賞された
小柴昌俊先生は、弊誌の巻頭対談(2007年9月号)で浜松ホトニクスの支援を強調され、観測施設「カミオカンデ」の装置の一部「光電子増倍管」の開発が、素粒子二ュートリノ観測に大きな役割を果たしたことを
を述べておられました。
しかし、最初から高度な技術があったのではなく、資金繰りに苦労され、毎日のように地元の有力者を回って「光の技術は国のために大変大事なものです。どうしてもやりたいので、何とか応援してほしい」と頼み込んだのです。
日本はなぜ、技術立国となったか
イノベーションを起こす上で、一番欠かすことのできないものが「熱意」です。管理力とは自社やお客様や製品や技術やサービスなどを、よりよくしていきたいという熱意のことです。晝馬さんは多様な創意工夫
をし、当時の社長を支援し続けました。
社長一人では、アフターコロナを乗り切ることは困難です。同じように、晝馬さんたちが手がけた光電管は厳しい船出で、不良品の山を抱えて失敗に失敗を重ねました。一五(同2)年には、やはりニュートリノの
研究で棍時隆載教授もノーベル賞を受賞され、当時、二人のノーベル物理学賞受賞に貢献できるとは夢にも思わなかったでしょう。
ドラッカー博士は「強みに焦点を合わせる」ことの大切さをどの著作でも述べています。特に「あらゆる企業、あらゆる組織が持つべき共通の強みがある。イノベーション能力である」(上田 惇生他訳『未来への決断ーダイヤモンド社)と、明確に述べています。
基礎技術では遅れていた日本企業が、なぜ技術立国となったのか。まさに日本の強みであるイノベーション能力を発揮して、実用化することに成功し、この国を豊かにしたのです。
イノベーションには思考の質が求められます。戦後日本の産業が世界に先駆けてイノベーションを起こして復興に貢献できたのは、経営者や経営幹部の思考の質が高かったからとも言えます。パナソニックの創業者である松下幸之助翁、ソニーの井深大氏、ホンダの本田宗一郎氏、トヨタ自動車の豊田喜一郎氏などに、「焦土と化した日本の再建」という大きな志が根底にあったからです。
管理力とは、セルフ・アウェアネス(自己認識・自己への気づき)の力です。自己への気づきの一番は、可能性です。あきらめたり、できない、無理だという感情のバイアス(ゆがみ)を、革新の嫉げとみなし、自身の可能性に挑む力を持つのです。浜松ホトニクスの成功は、畫馬輝夫さんの正しい自己認識にあったと思います。気づきこそイノベーションの源泉なのです。
本記事は、月刊『理念と経営』2020年11月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。
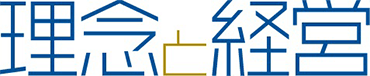


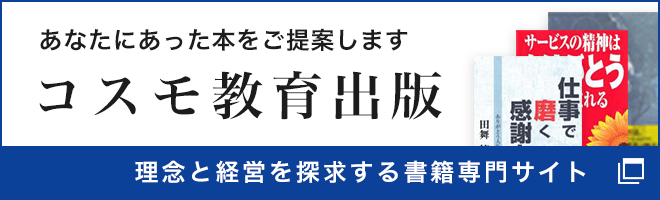





![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)