企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
管理力
2020年9月号
「成果」には「顧客の満足」がついてまわる
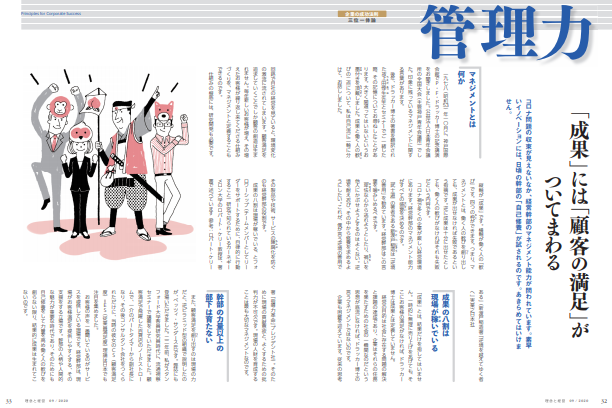
コロナ問題の収束が見えないなか、経営幹部のマネジメント能力が問。
われています。素早いイノベーションには、日頃の幹部の「自己修養」が試されるのです。あきらめてはいけません
マネジメントとは何か
1978(昭和53)年10月に、神戸国際会館でP・H・ドラッカー博士の記念講演をお聞きしました。公益法人日本青年会議所の全国大会(主管神戸青年会議所)でした。印象に残っているマネジメントに関する言葉があります。
後年、ドラッカー博士の著書を翻訳された故上田惇生先生とセミナーでご一緒した際、その記憶についてお尋ねしたことがあります。大きく間違ってはいないというお墨付きを頂戴しました。成果と働く人の歓びの二店についても、私は自己流に二軸に分けて、お話ししました。
縦軸が「成果」です。横軸が働く人の「歓び」です。四つの枠ができます。つまり、マネジメントとは、働く人の歓びを創り出しても、成果が出せなければ失敗であるという指摘です。逆に成果は十分に出せたとしても、働く人の歓びがなければそれも失敗だという内容です。
コロナ禍で多くの企業が厳しい経営環境にあります。経営幹部のマネジメント能力がすべての盛衰を決めるのです。
「武士道」の著者である新渡戸稲造は「逆境の善用」を勧めています。経営幹部はこの言葉を噛みしめるべきです。
「卑怯な心から逃れようとしたり、禍を他人にかぶせようとするのはよくない。逆境を耐え忍び、その中から修養を求めるようにしたい。これが僕の言う逆境の善用である。」(師戸部稲造著「逆境を越えてゆく者へ」実業之日本社)
成果の八割は現場が稼いでいる
「成果」とは、結果だけを指してはいません。一時的に無理に売り上げをあげても、そこにお客様の満足がなければ、ドラッカー博士は成果とは定義していません。
経営の目的は社会に存在する問題の解決と課題の達成であり、企業はそれらの任務を果すための社会の一機関なのだという思想が底流になければ、ドラッカー博士の言うマネジメントではないのです。
企業も困難を迎えています。従来の思考回路で自社の経営を見ていると、環境変化の激流に流されてしまいます。顧客満足を追求していくことでしか顧客の創造は生まれません。毎年新しいお客様が増え、その増えたお客様が繰り返し来て下さる仕組みづくりを、マネジメントと定義することもできるのです。
仕組みの根底には、研究開発も必要です。その製品や技術、サービスの陳腐化を防ぐのも経営幹部の役割です。
成果の八割は現場が稼いでいる、とフォロワーシップ(チームメンバーとしてリーダーをサポートするために、自律的に行動すること)研究で知られているカーネギーメロン大学のロバート・ケリー教授、著書で述べています(参考:ロバート・ケリー著「指導力革命」プレジデント社)。そのために現場の貢献意欲と、よくするための批判力が不可欠です。現場の人材を育成することは最も大切なマネジメントなのです。
本記事は、月刊『理念と経営』2020年9月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






