企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論
管理力
2018年12月号
経営資源が高度でなければ、”闘いの土俵”に上がれない
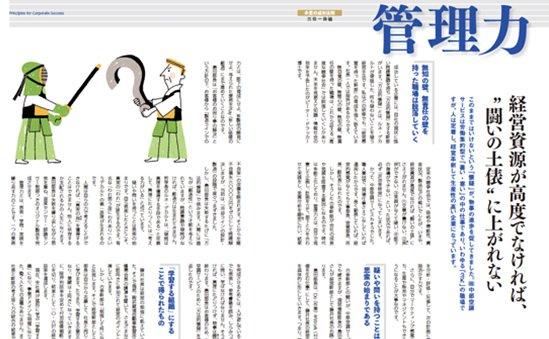
このままではいけないという「懐疑」が、物事の進歩を促してきました。
株式会社中部空調サービスは労働集約型で「暑い・寒い」の中の仕事であり、いわゆる「3K」の職場ですが、人は定着し、経営革新して生産性の高い企業になっています。
無知の壁、無責任の壁を持った職場は脱落していく
成功している企業には、自社の現状に強い問題意識を持ち「方法的懐疑」をする幹部がいます。
「方法的懐疑」とは、ルネ・デカルトが提唱した、何も疑わないことを疑う経営手法です。
私はどの研修でも、「経営感覚を持った幹部」の育成を強く訴えています。社長1人では限界があるからです。
無自覚の壁、無関心の壁、無知の壁、無責任の壁を持った職場は、これから迎える「高度な競争社会」では脱落していくしかありません。
未来を見据えて知識・情報社会の到来を予告したのがピーター・ドラッカー博士です。
従来の競争社会では、価格や機能性、資金状況、製品などの戦いでしたが、いまや、経営資源が高度でなければ〝闘いの土俵〞にさえ上がれません。
①文章が書けない、②挨拶ができない、③笑顔がなくて暗い、④部下の指導ができない、
といった状況であれば、必ず「非効率経営」になってしまいます。
かつて、中部空調サービスもそうでした。職人集団で、現場仕事さえこなしていれば通用したからです。
長く勤務していれば、経営的感覚がなくても工事部長、営業部長、所長、副所長になれたのです。
しかし、そうした古参幹部が会社の成長や発展を阻害する要因になるのです。
時代は多能工化しており、管理力とは、自分で発意して企画し、計画を立て、部下と力を合わせて実践をし、差異分析を緻密に行い、結果を分析・評価・反省して、次の計画に最大限活かす力です。
さらに、自分でマーケティング感覚を持ち、生産や販売やマネジメントもできるようになることが大事なのです。
疑いや問いを持つことは思索の始まりである
古参幹部との闘いが、中部空調サービスでも続きますが、現営業部部長の島田康信さんが経営幹部として藤井社長の右腕となります。
島田部長は、Do(作業)をWork(付加価値を生む仕事)にして、藤井社長の経営方針を具体的に形にしていきます。
つまり、管理力とは、部下の育成にせよ、新製品の開発にせよ、与えられた業務を Play (新しい価値の 創造)にまで高めていくことなのです。
本記事は、月刊『理念と経営』2018年12月号「企業の成功法則 社長力・管理力・現場力 三位一体論」から抜粋したものです。
成功事例集の事例が豊富に掲載
詳しく読みたい方はこちら
無料メールマガジン
メールアドレスを登録していただくと、
定期的にメルマガ『理念と経営News』を配信いたします。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






