導入企業の声
-
意見や表現は違っても、目指しているところは同じ

トーサイアポ株式会社
嘉藤 真也
会社情報:業種/自動車の小売り・整備・保険代理業
社員数/130名
社内勉強会導入時期/2007年8月トーサイアポ株式会社は、自動車卸販売商社として1966(昭和41)年に設立以来、今日の自動車社会の成熟と歩調を合わせ、自動車総合ディーラーとして確固たる基盤を築いてきました。国内で最も中古車ディーラーが多いといわれる埼玉県で、高いシェアを誇っています。
Q. 勉強会の開催内容を教えてください。
A. 毎月、1グループ7名の3グループで勉強会を実施しています。「理念と経営」の記事のなかから設問を1つ決め、その他に、この1カ月で印象に残った良い点、反省点を発表し合っています。
Q. 導入時にどんな苦労がありましたか。
A. 導入したばかりの頃は、グループ決めをする際に各自で日程を決めていたために、いつも同じメンバーになってしまうことが多々ありました。また、設問への回答もマンネリ化してしまっていました。
Q. 勉強会を開催するにあたり、どんな工夫をしていますか。
A. 導入時の状況を踏まえて、以来、グループ分けをする際に、部署や職種、年齢をバラバラにするように心掛けています。職種の違う者同士が集まることで、さまざまな意見が出てきます。
また、出てきた意見を認め合ったり、異なる意見を聞くことで互いを知り合うことにもつながり、コミュニケーションの向上につながっています。Q. 勉強会を導入したことで、会社に起きた変化を教えてください。
A. 以前に比べ、部署間の壁を感じることが少なくなり、連携もスムーズに進んでいるように感じます。意見や表現は違っても目指しているところは同じだということがわかることで、業務改善にもつながっているようです。
また、勉強会メンバーを毎回替えることで、今まで会話をしたことのなかった人と話をする機会にもなり、コミュニケーションも活性化しています。Q. 御社の強みを教えてください。
A. 社員さんです。一人ひとりが明確に明日の目標を見据え、全力で仕事に取り組んでいます。業績を伸ばせているのも、この社員さんの存在があってこそです。
これからも、「お客様、社員、社会に必要とされる企業の創造」の企業理念のもと、常にお客様にご満足いただけるワンランク上のトータルカーサービスの提供を追求します。 -
一人また一人と協力者が増え、あるとき、一気に空気が変わった
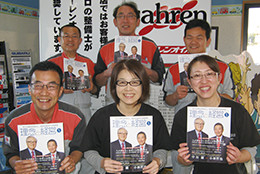
セキハツオートワークス有限会社
バイパス店店長 江澤 正人
会社情報:業種/自動車小売り・整備・保険サービス業
社員数/10名
社内勉強会導入時期/2008年「クルマ生活応援団」として、千葉県で自動車保険、新車販売、整備業を2店舗展開するセキハツオートワークス。地域密着を実現させている社員同士の結束は、社内勉強会によって高まりました。
Q. 社内勉強会導入のきっかけを教えてください。
A. 当時は社内のコミュニケーションが希薄でした。そこで、コミュニケーションの活性化と、「社員1人ひとりが人生の"成幸者"になる」という目的達成の手段として、導入を決めました。
Q. 導入した当初の様子はいかがでしたか。
A. まず、本を読むこと自体に抵抗を受けました。全体に否定的で、勉強会など受け入れがたい雰囲気でした。
そこで、社長や幹部数名が勉強会のサポートに入ることで、1人また1人と協力者を増やしていきました。そして、あるとき一気に空気が変わったのです。今では月に2回開催することが当たり前になっています。Q. 勉強会を導入したことで、会社に起きた変化を教えてください。
A. 普段、なにげなく話す言葉が前向きで主体的なものになりました。コミュニケーションも活発になったことで助け合う社風が構築されています。
また、その雰囲気がお客様にも伝わってリピートやご紹介にもつながっています。
「セキハツさんはいつもみんな頑張っているね」
「夜遅くまで熱心に会議しているよね。だから安心できるよ」
そうしたお客様からいただく温かい言葉は、〝志事〟のやりがいにつながっています。Q. 御社の人材育成にかける思いをお聞かせください。
A. 弊社のビジョンは「一生涯のお付き合い」「仲間とともに〝成幸者〟になる」です。1人ひとりが幸せを感じるためには、仲間と一緒に成長していることを実感できるということが大切です。
スキルやノウハウも大事ですが、それ以上に「人としてどうありたいか」を大切にしてほしい。特別なご縁で結ばれた仲間です。誰1人として脱落者は出しません。Q. 最後に、今後の抱負をお聞かせください。
A. 歩みは遅くても、仲間を思いやる優しさと、あきらめずに一歩踏み出す勇気、そして、人の可能性を信じることができる「人財」を目指して、共に学び続けます。
-
導入3年目で「勉強より仕事」と言わなくなって......

株式会社志賀商店
原 初
会社情報:業種/製造業
社員数/63名(パート・アルバイト含む)
社内勉強会導入時期/2010年志賀商店は豆一筋に60余年、「妥協なきものづくりは一流の証し」を信念に、豆の加工商品を扱う愛媛県の会社です。そのこだわりは生産地に足を運び、土質や気候を肌で感じとり、納得した原料しか仕入れないという徹底ぶりです。
Q. 社内勉強会導入時の御社の課題を教えてください。
A. 社内には複数の部門があり、他部門の人との交流は個人的に仲が良い人と以外はないという状況でした。そのため、スタッフの関心は自分の部署のみで部署間の協力関係も少なく、会社全体のことに関心をもつということもあまりありませんでした。
Q. 勉強会を開催するにあたり、どんな工夫をされましたか。
A. まずは全員が発言すると決め、マンネリを防ぐため、1年ごとにメンバーも入れ替えました。また、グループごとに開催日が異なるため、自分のグループの勉強会に参加できないときは他のグループの勉強会に参加するなど、参加しない月がないように工夫しました。
Q. 勉強会を導入したことで、会社に起きた変化を教えてください。
A. 社内のコミュニケーションが良くなってきたと感じ始めたのは導入して3年がたったころです。「勉強より仕事」といった言葉が聞かれなくなり、会議でも活発に意見が飛び交うようになりました。愛媛県から食品自主衛生管理認証制度(HACCP制度)で施設の認証が取得できたのも、成果の1つだと思います。
Q. 社員さんが勉強会で学んだことを仕事に生かすため、どんな取り組みをしていますか。
A. 勉強会での学びとして、会社を良くするためにどうしていけばいいか、それぞれ持ち場でのミーティング時に発表してもらっています。なかには「理念と経営」に登場した企業の事例から、自社に活用できそうなことを発表するスタッフもいます。
-
「人」が育たない企業に永続はあり得ません

株式会社感動コーポレーション
千葉 誠
会社情報:業種/サービス業
社員数/7名(パート1名含む)
社内勉強会導入時期/2008年感動コーポレーションは、「人のココロを動かして笑顔と元気を創造します」を経営理念にした、仙台市が拠点の販売促進支援会社です。会社案内やパンフレットといった紙媒体から、ホームページやECサイトなどのインターネットプロモーション商材など、独自の視点とアイディアで業績アップにつながる販売促進のお手伝いをしています。
Q. 社内勉強会の導入をされた目的は?
A. 本誌に登場するのが大手企業や有名経営者ではなく、私たちと同じ中小零細企業というところが素晴らしいと思いました。経営者だけでなく、幹部社員、現場社員と、それぞれの視点で考えさせられる内容でしたので、OJTの取り組みの1つとして導入しました。
Q. 勉強会開催にあたって工夫したことは?
A. もともと本を読むことに慣れていない社員さんがほとんどでしたので、「面倒くさい」という意見が多く上がりました。そこで、まずは勉強会に興味があり、「やってみたい」という社員さんだけで開催することにしました。お菓子や飲み物を用意するなど、気軽な気持ちで臨める空間づくりにも心掛けました。
Q. 社内勉強会を導入したことで、会社に起きた変化を教えてください。
A. 社内のコミュニケーションが活発になり、風通しの良い社風になったと思います。ざっくばらんに意見を出し合うなかで、それぞれがどんな考えで業務に臨んでいるのかという点を共有できたことが大きな要因ではないでしょうか。また、物事を人に伝える能力も目覚ましく向上したように感じます。
Q. 御社における人材育成の位置づけ、また、それにかける思いを教えてください。
A. 企業経営は何をするにも「人」がすべてだと考えます。お客様の所に伺いニーズをお聞きすることも、それをカタチにすることも「人」と「人」とのつながりがあるからこそできることです。もちろん経営者も「人」です。故に「人」が育たない企業に永続はあり得ません。今後も「人財育成」に全力を投じ、企業経営に臨みます。
-
「読まれている」という意識が取り組み姿勢を変えた
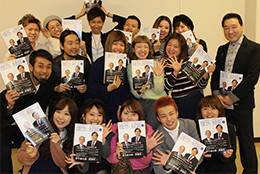
ザッツ・コーポレーション株式会社
藤内 義久
会社情報:業種/美容業
社員数/54名(保育士3名含む)
社内勉強会導入時期/2007年ザッツ・コーポレーションは、大阪市に6店舗を展開する地域密着型の美容室です。「快適空間の創造」という理念のもと、お客様1人ひとりの要望に合わせたヘアスタイルを提供するために、スタッフの人間力向上に力を注いでいます。
Q. 社内勉強会の導入をされた目的は?
A. これまでは、理念の浸透と意思統一を目的に定期的に個人面談を行なっていましたが、スタッフが増えるごとに時間の調整がしにくくなっていました。そこで、勉強会がそうした場になればと思い、始めました。
Q. 社内勉強会を導入したことで、会社に起きた変化を教えてください。
A. 初めは経営者を含めた店長・副店長メンバーで開催していましたが、記事の感想止まりで自社への落とし込みまで話が及ばず、設問表も書き込みが少ない状況で、活発な会とは言えませんでした。
ところが、導入2年目に思い切って全社員参加に切り替えたところ、若いスタッフを中心に熱心に参加してくれたのです。「先輩・後輩が共通のテーマでディスカッションする」ということを楽しむことで、お互いを理解し、人間関係の向上にもつながっています。Q. 導入に成功した要因は何だったと思いますか。
A. ある時期から、スタッフが記入した設問表すべてに経営者が赤ペンでコメントを書いて返却するようにしました。すると、「読まれている」ということを意識して、よりしっかり記事を読み、自分の考えを書くようになりました。
経営者にとって、社員さんの考えていることがわからないことほど不安なことはありません。コメントを書きながら気づかされることも多く、経営者にとっても一番の勉強になっています。Q. 御社における人材育成の位置づけ、また、それにかける思いを教えてください。
A. 美容業界は人材育成に尽きます。技術はできて当たり前で、その技術をどれだけお客様満足に結び付けられるかは、相手の気持ちを汲み取る能力にかかっています。さまざまな企業の事例は、考えを幅広くもつための知識の源となっています。
-
社員さんが会社の強みになればまねのできない差別化につながる

株式会社コンフォール
原 文典
会社情報:業種/ビルメンテナンス・医療施設サポート・指定管理者事業
社員数/529名(パート社員さん含む)
社内勉強会導入時期/2007年長野県松本市に本社を置くコンフォールは、お客様より信頼をいただくことを喜びとして、ビルメンテナンス、医療現場のサポートサービス、行政の指定管理者事業の三大事業を展開しています。
Q. 社内勉強会の導入をされた目的は?
A. 社員さん1人ひとりに経営感覚を身につけてもらいたいとの思いからです。サービス業において、お客様から信頼をいただくために1番求められることは社員さんの「質」です。社員さんが会社の強みになれば、他社にまねのできない差別化にもつながると信じ、導入を決めました。
Q. 社内勉強会を導入したことで、会社に起きた変化を教えてください。
A. 他社の成功事例を読むことで、社員さんの経営知識が徐々に深まり、会議などでアイディアが豊富に出るようになりました。
また、部門に関係なくチーム分けをしたことで、部門の壁を越えたチームワークが醸成され、社内のコミュニケーションが活発になっているのを感じます。Q. 社員さんが、学んだことを仕事に活かすため、どのような取り組みをされていますか。
A. クレーム発生時や改善提案活動に個人の意見をより反映しやすくするために、全体で話し合うのではなく、小グループで意見を出し合う場を作るように変えました。
Q. 御社における人財育成の位置づけや、それにかける思いを教えてください。
A. 弊社のような労働集約型の業種で差別化を実現するには、「人財」の育成が非常に大切です。おもてなしの心や、技術・知識の差がそのまま業績の差につながるからです。よりお客様に喜んでいただける企業にしていくためにも、教育カリキュラムや人事評価制度で自社独自の「人財」を育てていくことがわが社の生命線です。これからも凡事徹底、計画性、学ぶことを大切に、日々コツコツと努力を続けてまいります。
-
人「財」になったとき、会社は自然と繁栄し、永続できる

株式会社 びわこホーム
髙木 光江
会社情報:業種/不動産・建築業
社員数/36名(役員4名含む)
社内勉強会導入時期/2006年びわこホームは1990(平成2)年の創業以来、徹底した地域密着型経営で土地、建物の販売等を中心に事業を展開し、滋賀県甲賀エリア売り土地物件占有率77%、建築棟数13年連続№1という実績を上げています。
Q. 社内勉強会の導入をされた目的は?
A. 幹部・社員さんにもっと経営感覚をもってもらい、「会社をよくしたい」と自発的に積極的に行動できる人財を育成していくためです。たくさんの事例からいろんなことを学びとり、それぞれの仕事で活かしてほしいという思いもありました。
Q. 社内勉強会を導入したことで、会社に起きた変化を教えてください。
A. それまで上司に頼りがちだった社員さんたちに、まずは自分で考えてみるという癖・習慣が身につきました。問題解決に前向きに取り組む社員さんが増えました。また、お客様やお取引先からは「びわこホームの社員の誰と接しても元気で気持ちがいい」「自分(お客様)に元気がないとき、びわこホームの社員さんに電話をかけて話をすることで元気をもらえた」といったお声を多くいただき、協力業者さんからは、「現場の5Sができている」「現場がスムーズに進む」というお声が寄られています。
Q. 社員さんが、学んだことを仕事に活かすため、どのような取り組みをされていますか。
A. びわこホーム社員以外の協力業者さん・パートナー企業さんと共に「理念と経営」を通して学び、ディスカッションしています。それぞれの立場からの熱い念いや意見を交換することで、お客様が喜んで幸せになっていただく家づくりができています。
Q. 御社における人財育成の位置づけや、それにかける思いを教えてください。
A. 経営者の使命は社員さんを幸せにすること、業績を上げること、繁栄し永続することです。中でも人財育成が一番重要と考えています。わが子のように念っている社員さん自身が成長し、社員さんの人生目標をびわこホームで働いて達成していってほしい。人財教育に掛ける愛情、情熱、お金、時間は惜しまず、命を懸けています。人「財」になったとき、会社は自然と繁栄し、永続できると信じています。
-
お客様が大粒の涙を流して感激した、社員の提案による〝サプライズ〟

有限会社 サンエイ企画
金村 永治
会社情報:業種/遊技業
社員数/45名
社内勉強会導入時期/2008年1月福岡県福岡市で遊技場を運営するサンエイ企画は、2017(平成29)年に創業45年を迎えます。「すべては『ありがとう』と『感動』のために」という理念の下、2店舗、45名の社員が一丸となり、明るく楽しい遊技空間をつくる努力を重ねています。
Q. 社内勉強会の導入を決めた経緯は?
A. 経営者として学ぶなかで本誌を読み、私自身の学びになることはもちろんですが、経営に関するヒントが多くあり、「これなら全社員さんで読めば、異業種からの学びが社内での提案や改善に役に立つ」と思い、ほとんど私の一方的な考えで始めました。
Q. 当初、社内の反応はどのようなものでしたか?
A. 最初の1年くらいは、あまり変化という変化は感じませんでした。勉強会リーダーを男性社員から女性社員にした頃から、少しずつ社内でのコミュニケーションが良くなり、会社全体が明るくなった印象を受けました。
後から聞いたところによると、最初の頃は社員さんから「社内勉強会をやって何の意味があるのか?」という批判の声もあったそうです。今では、社員さんからの多くの提案や改善が、お客様からの感謝の言葉となり、それが社員さんにとっても励みになっているようです。Q. 勉強会を続けたことで、会社に起きた変化(社風・業績・人材)を教えてください。
A. 導入してから2年くらい経った頃から、社員さん1人ひとりがお客様の目線で自分の考えていることを発言するようになりました。それが仲間同士で良い影響を与え、会社全体が活性化し明るくなりました。
例えば、こんなことがありました。ある日、1人の女性社員がお客様との会話の中で、そのお客様が重い病を患っておられることを知りました。そこで「千羽鶴」を折りましょうと全社員に声を掛けました。その後、そのお客様が来店された際にお渡しすると、お客様が大粒の涙を流されて感激されました。社内勉強会でお客様のお困り事を解決するために、行動できたおかげです。Q. 社員さんが学んだことを仕事に活かすため、どのような取り組みをされていますか?
A. 気づきや学んだことを朝終礼時に発表したり、実行したことの進捗発表などを行なっています。社員さんからの提案や改善案は、社員さんの考えを重視して全社で取り組んでいます。
また、職場内訓練(OJT)として、「理念と経営」社内勉強会のほか、毎日の地域清掃活動、活力朝礼、「13の德目」朝礼、社内委員会活動なども実施しています。それらによって、地域の皆様やお客様と明るく元気な挨拶を交わし、笑顔でコミュニケーションがとれるようになりました。これからも心身共に健康で生き生きとした社会生活と人のお役に立てる素晴らしい人間性と人間力を身につけてまいります。より良い会社、より強い会社、より良い社風を目指します。 -
部署を超えた意見交換を通して社内のコミュニケーションが活性化

藤安醸造株式会社
藤田 幸一鹿児島で1870(明治3)年創業という長い歴史をもつ同社は、「ヒシク」ブランドの味噌・醤油・食酢等の調味料を主力商品とし、県内はもとより、大阪、東京をはじめ、海外にも積極的に営業活動を展開しています。鹿児島の味覚文化を広く発信しながら、食の多様化に対応するために、社内勉強会や技術研修を通じて組織全体で人財育成に力を注いでいます。
Q. 勉強会を導入する前、どのような課題をおもちでしたか。
A. 部や課を超えたコミュニケーションが不足していました。そのため、社内の情報共有がうまくできず、社員さんが自分の仕事にばかり意識が向きがちで、視野を広げることがあまりできていなかったように感じます。
Q. 社内勉強会を始めたとき、社員の皆さんの反応や様子はどうでしたか。
A. 社員さんにとって本を読むこと、設問表に答えることが少なかったため、なかなか設問に対する答えが出ないことがありました。相手の意見を否定することなく継続することによって、少しずつではありますが、社員さんの設問に対する回答の中身が充実していきました。
Q. 継続していくなか、会社に起きた変化を教えてください。
A. それまでは自分の課や部内だけの関わりであった社員さんが、勉強会で他の部署の社員さんと意見交換することを通して、お互いの考え方や仕事についての理解が深まり、社内のコミュニケーションの活性化につながりました。
また、勉強会の導入によるものかはわかりませんが、社員さんが自らお客様に挨拶やお礼の手紙を書いたり、お客様第一で行動したりするようになり、得意先から「初めて取引先の方から手紙をもらいました」「いつも良くしてもらっているよ」といったお褒めの言葉をいただくことが増えました。
Q. 導入に成功した要因は?
A. 実質的な勉強会の運営を社員さんに任せていることだと思います。それによって、社員さん1人ひとりが自ら勉強会のメンバーを巻き込んで行動するようになっています。具体的には、チーム編成を1年ごとに行ない、より多くの社員さんとコミュニケーションをとれるようにしています。若い社員さんにチームリーダーを任せたり、司会や書記を代えたりすることによって全員参加型の勉強会になるようにしています。社員さんの設問に対する答えに対して社長が目を通し、コメントを付けていることも成功要因の1つだと思います。
Q. 社内勉強会を通じ、藤田様ご自身が得た気づきや学びを教えてください。
A. 何事も取り組む際は、真剣さと継続が大切であると気づくことができました。また、社員さん同士で意見交換ができてきたことで、相手の立場を考えて行動するようになりました。そして、本誌を読むことで知らなかった言葉も学ぶことができ、「臥薪嘗胆」という言葉は私の座右の銘として、仕事がつらいと思ったときなどに自己の戒めの言葉になっています。
会社情報:業種/味噌・醤油等調味料製造販売
社員数/69名
社内勉強会導入時期/2008年8月 -
「どう活かすか」を発表することで学びを深く落とし込める

美容室フレーム
鍋島 道樹広島県東広島市を中心に国内11店舗、タイのバンコクに1店舗展開している同社は、地域密着型の美容室として親しまれています。2008(平成20)年の社内勉強会開始以降、もともと明るい社内にさらに明るい笑顔が広がっています。
Q 社内勉強会を導入した目的を教えてください。
A 他業種の会社の成功体験や成功事例などを全社員で学び、共有することにより、1人ひとりが考え、行動に移せる率先垂範の組織づくりができると思ったからです。また、勉強会では4~5人のグループに分かれてディスカッションをします。その中で、自分の想いを要約し、グループ内で発表します。仲間の発表を傾聴、承認することで、接客業に必要なスキルを身につけると同時に、人としての在り方を考える機会になると思い、導入しました。
Q 実際にはどんな変化がありましたか。
A 店舗数が増え、社員さんの数も増えた時期と重なったため、コミュニケーションをとるちょうどいい機会になりました。毎回グループのメンバーをシャッフルすることで、他店舗のメンバーと話すことができ、本音で話せる組織へと変革していったと感じています。
Q 導入後、お客様や取引先に喜ばれたエピソードがあれば教えてください。
A 「いつ来てもウェルカムな雰囲気で、どの社員さんも話しやすい」「とにかく明るい社風だ」という声をよくお聞きします。臨店講習などで来ていただく講師の方からは、「本当に元気な社員さんで雰囲気がいい。こんなサロンはないよ!」と有り難い言葉をいただきました。
Q 導入に成功した要因は何だったと思いますか。
A 楽しんで取り組んだからだと思います。また、グループごとにディスカッションを終えて何を感じ、今から何を変え明日から仕事で具体的にどんな行動をとっていくかについて発表するようにしています。そうすることで、1人ひとりが社内勉強会の内容をより深く落とし込むことができ、他業種や自分以外の人のいいところを仕事に活かすことにつながっています。
会社情報:業種/美容業
従業員数/正社員55名、パートナー社員21名
社内勉強会導入時期/2008年









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






