導入企業の声
-
社員さんの成長を一番実感する教材であり、勉強会です

有限会社オーリー
太田 利昭弊社はタイヤ販売店です。島根県は降雪地区で、10万人の人口に対してタイヤ販売店の数が最も多い県でもあります。創業当時は、タイヤメーカーの下請け作業をメインに行い、次第に自社での販売へと移行していきました。
下請け作業がメインの時は、「勉強なんかしなくても依頼されたことをきちんと行えば良い」と思っていました。しかし、一般のお客様を増やしていこうとすると、接客応対、店舗立地、自社認知などの問題が起きてきました。
私も、このままではいけないと経営の勉強を始めました。しかし、学べば学ぶほど、現場の社員さんとの温度差が出てきました。「自分ばかり勉強していたのでは会社はよくならない」。そうした中で、社内勉強会を導入しました。
すぐには結果が出ませんでしたが、1年、2年と続けていくと社員さんの発言の中に経営理念が飛び交うように!考え方だけでなく行動にも変化が出てきました。お客様から「気持ちの良い対応をしてもらったよ」とお手紙をいただけるように!今では弊社にとってなくてはならないツールです。 -
勉強会によって、どんな場面でも堂々と発言できるように
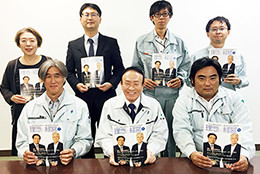
杉林建設株式会社
杉本 友子「世に必要とされる会社を目指し、人に必要とされる人間を目指す」を経営理念とし、愛知県岡崎市で総合建設業を営んでいます。明治40年創業で、会社組織としては設立55年目を迎えました。
経営方針を基に毎年、個人の行動方針書を作成し全員参加型の「経営指針書」を作り始めて今年で17年目です。作成にあたり、一人ひとりの目標を会社の方向性と合致させるには、やはり社員教育、それも共通言語を用いた社内教育が不可欠と感じていました。
『理念と経営』を用いた社内勉強会は6年前から始めました。月に2回、会議の後に1時間ほど開催しています。続けていて良かったことは、社外で発言の機会があった時、自分の意見をわかりやすく明確に相手に伝えられるようになったことです。社内勉強会で自分の感想や意見を繰り返し発表することでコミュニケーション能力が向上し、どんな場面でも臆せず堂々と発言できる力が備わったのだと感じています。
『理念と経営』を通して全国の企業様の取り組みや理念経営に触れることで、もっと社会のお役に立ち、必要とされる会社、人間になろうと気持ちが引き締まります。
時には話が脱線しますが、それもまた楽しみながら、最後は笑顔で会を終えるようにしています。 -
〝人財育成〟こそが、より良い仕事を生む源泉になる

有限会社いすい
宮城 信孝弊社は、一般クリーニングを基本業務に徳島県下で8店舗を運営しています。
社内勉強会の導入目的は社風を良くし、学ぶ環境をつくるためです。当時の社内は店舗と工場が対立し、お互いを認めていませんでした。「自分たちが扱っているのはお客様の大切な商品」という意識も薄かったと思います。
導入後、最初の1~2年はあまり変化を感じられませんでした。やらされている感いっぱいで、あるパートさんは「なんで仕事以外に時間を取って、こんなことせんとあかんの?」と参加しなくなってしまいました。
変化を感じるようになったのは、「13の德目」を使った朝礼を、社員さんの提案で始めてからです。朝礼との併用が相乗効果を生んだように感じます。現在は、10名で始業前の7時30分から開催し、遅くとも8時45分には終わるように気をつけています。
当社は、お客様の商品をお預かりし、きれいにしてお返しすることをなりわいにしています。商品に思いを込めることが仕上がりに影響します。〝人財育成〟こそが、より良い仕事を生む源泉になると思います。 -
経営者と幹部二人の勉強会は月1回の「幹部教育の場」

株式会社ジン・コーポレーション
炭屋 昭一郎大手ゼネコンの2次下請けとして東京・神奈川を中心に都市型土木工事に従事しています。管理職2名、現場従業員16名の、創業15年目の会社です。
勉強会は7年前に始めましたが、最初は仕事を優先しがちで開催は不定期でした。しかし、3年前に現場従業員が管理職になったことを契機に、社長と幹部の2人で「幹部教育の場」として月に1回開催するようになりました。
設問表の回答に対して、コーチングを意識した質問を投げかけるようにしています。仕事観や人生観にまで掘り下げたり、実務に生かせる具体的な話を引き出すように心掛けたことで、記事からの学びが理念的視点と経営的視点が結びつく場になってきたと感じています。
時間をかけてじっくりと話し合うことで、深いコミュニケーションの場となっています。さらに、記事からヒントを得て自社のサービスを向上させるアイディアが見つかったり、ときには悩み相談の場になったりと、毎回新しい発見を得ながら楽しく学んでいます。 -
否定せず、承認し合うことで社風の改善を実感

有限会社寿昇運
赤羽 昇当社は、長野県松本市に本社を置く、創業20年の運送会社です。「矜持の想配送業者」を旗印に、信州と中京、関西をつなぐ動脈として信州の豊かな生活環境を支えています。
また、自然環境を支える取り組みとして、廃てんぷら油を原料にしたバイオディーゼル燃料を、自社で製造して全車の燃料に使用することで、CO2削減に取り組んでいます。
社内勉強会の導入目的は、お互いが助け合い、支え合う社風をつくるためでした。導入から3年たちますが、「否定しない」というルールのもと、相手を承認することで、社風の改善を感じています。
そう実感する理由は、3つです。1つ目は、同じ記事を全員が読むことで共通言語が増えたこと。2つ目は、理念経営の大切さへの理解が進み、理念につながる意見も出てきたこと。そして3つ目は、社員とお客様との関わりが増え、紹介案件が増加していることです。
今年の工夫点として、「方針手帳」に設問ページを組み入れることにより、1年分の勉強会の内容を振り返れるようにしています。また、設問を工夫することで、社員の理念行動を集め、事例集の作成にも取り組んでいます。 -
目的を明確にした勉強会で風通しの良い社風を実現したい

大森商事株式会社
占部 有輝弊社は岡山市の東区・中区を中心に、賃貸管理を中心とした不動産業を営んでいます。過去に1度、社内勉強会を導入しましたが、「仕事が優先」という意識が強く、社員さんの集まりが徐々に悪くなり、いったん中止していました。
2年前から、「人財育成をしなければ業界から淘汰される」という思いから再度スタートしました。月に1回、会議後に1時間の勉強会を行なっています。過去に1度中止となったことを振り返ると、会の目的が不明確だったのだと思います。現在は、社内でのコミュニケーションの活性化など、〝3つの目的〟を明確にした上で取り組んでいます。
また、正社員だけでなく、会議に出席できないパート社員さんにも設問表の提出を義務化しています。勉強会の中では、お互いに仕事に対する考え方や体験談に触れることで、経営理念の浸透や価値観の共有を図っています。
今年、弊社は創業55年の節目を迎えています。企業の命題である〝永続発展〟のためにも、経営理念・経営ビジョンを浸透させ、風通しの良い社風を実現していきたいと考えています。 -
社内勉強会は良い社内のコミュニケーションツール
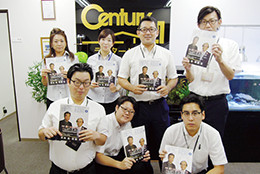
株式会社ラスターハウス
小澤 孝一郎東京・大田区で不動産の売買仲介と賃貸仲介の営業を始めて10年の節目を迎えました。「おもてなしの心をもって東京の不動産を活性化させること」を使命に、「365日営業、いつでもつながる」ことを強みにして、地域の方々に愛される店舗づくりを目指しております。
勉強会は初めから全員参加で行ないました。当初は、「いまさら勉強するのは嫌だ」「自分の想いを他の人に発表するのは抵抗がある」などの否定的な意見が多くありました。しかし、続けていくうちに、「仲間の新たな一面を発見できた」「仲間の意見を聞くことが楽しい」などの肯定的な意見に変わっていきました。
数年前からは、設問表を当社独自で考えて、それを基に勉強会を開く形になりました。最初は社長が社員に聞きたいことを中心に作成していましたが、その後は幹部で、そして今では社員全員がローテーションで設問を考えています。自ら設問を考え、回答をすることによって、社会や業界、会社に対する想いが深まっていると実感しています。
勉強会はとても良い社内コミュニケーションツールです。これからも楽しく続けていきます。 -
毎回、社外のゲストが参加することがいい刺激に

キューハイテック株式会社
日髙 美治弊社は福岡市で給排水衛生設備、主に都市ガス設備の設計・施工を行なっています。スタッフは総勢約50名で、うち約半数は建設現場で配管工事を担っている工事士です。 勉強会は、創刊から10年以上、毎月欠かさず続けています。2、3名しか参加しないといった時期もありましたが、今では冬場の繁盛期を除き、ほぼ100%に近い参加率になっています。
わが社の勉強会の特徴は、以下の6つです。
1つ目に、設問表は社員がもち回りで作成していること。2つ目に、提出された設問表に対する赤ペンでのコメント書きも社員全員で行なっていること。3つ目は、勉強会の始まりを必ず社員同士のハイタッチでスタートすることです。
4つ目は、お茶とお菓子を食べながら、楽しくディスカッションする雰囲気を全体でつくる。5つ目は、話の流れで設問表から外れることがあってもOK。そして、6つ目は、毎回ゲスト参加を募り、社外の方たちと社員が会話できる機会をつくっていることです。今では、ゲストの参加も多いときには10名近くにもなり、いい刺激になっています。 -
会議前に勉強会を開催することで会議でも前向きな意見が出ます

オートライフダッシュ株式会社
加藤 勝敏弊社は25年前に、自動車学校の教習車の整備を兼ねたディーラーとして創業しました。そして、5年前に「地域の方のお役に立つコミュニティー空間」というコンセプトを掲げて独立、再スタートを切りました。
「車屋さん」というと、営業とメカニック部門との不仲をよく耳にします。10年前に社内勉強会を導入しましたが、最初の数年は、意地の張り合いや自己主張をする発言が多く、思い描いたイメージとは程遠いものでした。しかし、日頃の鬱憤を出し切ると、次第に前向きな発言、他人を敬うような一面がみられるようになりました。
現在は、過去に掲載された「理念と経営」社内勉強会報告を参考にして、勉強会を月に1度の全体会議の前に行なっています。そうすることで、勉強会後の会議でも「発言したら損をする」といった雰囲気が払拭され、活発に意見が出るようになりました。今では、会社、部門、個人、お客様全体を考えた、前向きで有意義な会議になっています。
これからも、弊社のコンセプトを実現するためにも勉強会を通じて社内コミュニティーを大切にしていきます。 -
コミュニケーションには〝きっかけ〟が必要だと実感

旭建設株式会社
西田 貴兵庫県尼崎市で創業84年になる建築会社です。「職場環境サポート業」を事業領域として、工場をメインに幅広く地域社会に貢献する、社員9名の会社です。
社内勉強会は、営業のスキルアップとチームワーク向上を目的に始めました。毎月第3金曜に、社長が作成したオリジナルの設問を基に、ディスカッションを中心とした勉強会を開催しています。
導入当初は日程も固定ではなく、現場での仕事が多いために遅刻や欠席が多く、なかなか全員での開催が困難な状況でした。そこで、日程を第3金曜に固定したことで参加人数が徐々に増え、今ではほぼ全員が参加するようになりました。参加率の増加とともに、発言も活発になり、社内のコミュニケーションも良くなってきたと感じています。意見交換のなかで、仕事への考え方を見直すきっかけになったり、改善点の発見につながったりもしています。
勉強会での変化から、コミュニケーションには〝きっかけ〟が重要なのだと実感しています。今後は、より質問しやすい職場環境をつくれるようにしていきたいと思います。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






