導入企業の声
-
何のために理念があるのかを理解できるようになった

株式会社マルワ
関根 健輔当社は、本社を茨城県水戸市に置き、タイヤ整備機器、タイヤ補修材の卸売り販売とアフターサービスを北関東、東北地方中心に行っております。「成長と感動を自覚して満足を与えます」を経営理念に掲げ、お客様第一主義をモットーに、お客様が必要とする商品、サービスを一貫してお届けしています。
共に学ぶ会を始めて、366回になりました。私が入社したときには、すでに行っていましたが、共に学ぶ会を導入した当初は、設問表に未記入で参加するメンバーや参加をしないメンバーもいたそうです。今では従業員全員が参加し、設問表にもすべて記入した状態で参加しています。
また1人ひとりが積極的に発表をして、それぞれがそれについてのフィードバックし、真剣かつ楽しく会を行っています。
この勉強会を通して自社の経営理念について深く知り、何のために理念があるのかを理解できるようになりました。
お客様のために自分たちは何ができるか、どうすればもっと喜んでいただけるかを日々追求しています。これからもお客様の喜びと自己成長のため共に学ぶ会を続けていきます。 -
独自の設問を作り、戦略思考を身につける

富士凸版印刷株式会社
山本 登美恵名古屋の地で創業55年を迎える、総合印刷業の会社です。当社の経営理念は「想いをかたちに」です。お客様のビジョン実現のお役に立つため、自社の事業領域で何ができるかを、第2土曜日に戦略勉強会、第4土曜日に『理念と経営』共に学ぶ会を開催し、学んでいます。
『理念と経営』に掲載されている企業事例を基にオリジナルの設問を考え、チームでディスカッションし、戦略勉強会で学んだ知識を深めています。
特に企業事例研究などでは、どのような戦略でお客様の喜びを得ているのか深く考え、自社に置き換えたらどうかなど深掘りをしています。
自社はどんな商品・サービスを提供していきたいかという具体的な話になると、皆、本当に自由な発想が飛び交い、とても有意義で楽しい時間になっています。設問の答えの中から実際に改善提案や商品開発に向けてのヒントも出ています。
戦略思考と企業事例のケーススタディーを分析する社内勉強会は、弊社にとって未来のイノベーションを起こす土台づくりです。 -
朝礼に組み込んで継続的に開催

Aテクニックデンタルラボラトリー株式会社
跡部 雅彦当社は歯科技工所です。「私達は『しごと』を通して自分を磨き続け皆様と笑顔を共有します」を経営理念として、お客様である歯科医院様のためにセラミックの歯や入れ歯などの補綴物を製作しています。患者様の利益を第一に考えて、高い付加価値を提供しています。
「共に学ぶ会」は5年前にスタートしました。初めは設問表の記入欄も1行ぐらいで、それを読み上げるだけの内容でした。
しかし、現在ではひと月の中で5日間、「13の德目」朝礼に組み込む形で継続しています。
考える習慣が身についてきたことで発言・表現が自分の言葉でできるようになり、仲間の発表に対しては傾聴し承認して共感できるようになりました。また、報連相、確認が自発的になり、ミスが発生してもリカバリーし合うようにもなりました。
この会が社員さんのチームワークに影響していると感じ、嬉しく思っています。
『理念と経営』に掲載されているさまざまな企業事例から視野を広げ、健全な価値観を育み、全員経営を目指すことでお客様から信頼され、なくてはならない会社に成長発展していこうと思います。 -
認め合い支え合う社風づくりに欠かせない
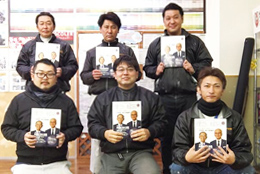
有限会社新栄塗装工業
甲斐 隆弊社は今期で45期目を迎える、住宅の外壁屋根等外装改修工事をメインとした、住宅リフォームの会社です。
「人が輝く街づくり・未来づくり」という経営理念の下、「住宅リフォームを通して、地域の皆様、社員さん、関わる全ての人たちの人生を輝かせる!」、そんな思いで日々励んでおります。
弊社では設問表にしっかり取り組んでこれなかった人へ30分〜1時間程度の設問記入の時間を設もうけています。設問はその時々の自社の成長課題に合わせて作成し、お菓子や軽食なども用意して和やかな雰囲気で開催できるよう工夫しております。
導入して4年目になりますが、確実に社員さん一人ひとりの意識や使う言葉の質が変わってきたと感じています。何より、「去年の今ごろはこんな会話できていなかったよね!」と社員さんから言ってもらえたことが嬉うれしく、続けることの大切さを感じました。
月1回互いの「仕事への念」を共有する場として、認め合い支え合う社風づくりに欠かせない時間となっております。 -
仕事では聞けない価値観を知ることができる場

有限会社楽笑
川崎 奈月兵庫県に四店舗(屋号dot.hair)を展開している美容室です。
わが社には理念委員会があり、理念委員会のメンバーで設問表を考え、月1回、勉強会を開催しています。
設問に対してディスカッションをし、深掘りをすることで、仕事中ではなかなか聞けない個々の考えや価値観を知ることができるようになりました。
最近では、スタッフから発表の中で「こうしていきたい!」や「こうなりたい!」という前向きな意見が出るようになりました。また、ディスカッションでは先輩が後輩へアドバイスや経験談を話し、明日からの仕事に生かせるようにいろんな方法や考えを伝えるようになりました。
設問表には、社長の赤ペンで返信もあります。勉強会が終わった後日、社長の考えもプラスされることで、さらに深めれる勉強会になっています。
これからも理念委員会を中心に「美しさを共に創り最高の笑顔に」の経営理念が社内により浸透するよう学んでいきたいと思います。 -
考え方を知ることが信頼関係構築につながる

第一商事株式会社
清水 聖也当社は静岡県・中遠地区の豊かな暮らしのサポートをするエネルギー会社です。
今年で設立57年を迎え、関わるすべての人にとって「なくてはならない会社」であり続けるという企業理念の下、ガソリンスタンド、LPガス、リフォーム、コインランドリーなどの事業を中心に展開しております。
当社では共に学ぶ会を「共有会」と呼び、毎月1回、10名で開催しています。
毎回メンバーは社長の私がランダムに人選します。部門や役職、年齢を超えて1つのテーマと向き合い、ディスカッションすることで、仲間の考え方や意見の発信の仕方を知ることができます。それが相手へのリスペクトや信頼関係の構築につながっていると感じています。
また、他社の成功事例や経営者の体験談に触れることで視野が広がります。それにより自社の強みなどを再認識でき、仕事の目標や指針を自ら考え行動する力が付く機会となっています。
何より、私の思いや考え方を発信する貴重な場となっています。 -
個性を認め合う楽しく有意義な場

株式会社インテリア紅葉
佐々木 剛弊社は、創業47年目を迎える、壁紙やカーテンなど内装仕上げ工事の専門店です。
「"住まいを彩ること"でお客様と一緒にHappyLifeを創る」を経営理念とし、インテリアを通じてお客様と一緒に暮らしや人生の楽しみを創り出すことに励んでおります。
初めは誰も参加してくれないのではないかと不安でした。ですが、素直で前向きなスタッフのおかげで反対もなくスタートしました。
しかし、数カ月がたつと、ただ参加するだけ、仕事が優先で欠席や遅刻も多い状況となりました。そこで、目的をコミュニケーションに絞り、ランチを全員で食べ、和やかな雰囲気で勉強会をするようにしました。すると少しずつ本音で語り合えるようになりました。
また幹部社員さんの協力がとても良い影響を与えています。自由な発言ができるようにサポートしたり、リーダーとなって運営したりとチームワークが良くなってきたと感じます。
お互いの個性を認め合い、プラス思考で意見を出し合う場として、楽しく有意義な勉強会をこれからも続けていきます。 -
コミュニケーションの質が高まり、絆が深まる

ティ・アイ・エス株式会社
盤若 玲奈当社は、「お金に困らない人生をサポートする」という経営理念のもと、北陸3県で保険代理業、住宅相談業を行っています。
共に学ぶ会では、ただ自分の意見を発表し合うだけでなく、出てきた意見に対して、「なぜそう思ったのか」という根本的な考え方を聞いています。
これによって、同じ職場で働く仲間との価値観の共有ができ、また新たな考え方の発見にもつながっています。
この共に学ぶ会を行うことで、普段の会話だけでは気がつかない、仲間の考え、思いを知ることができているのです。
また、職場でのコミュニケーションの質がより高まり、メンバーとの絆が深まったと感じています。
「相手を知ることで、より相手とのコミュニケーションが円滑になる」というこの学びを、社内ではもちろん、お客さまとの会話でも意識していくことで、より深い信頼関係を築いていきたいと思います。 -
スタッフの成長が実感できる共に学ぶ会

有限会社セッション
伏原 一徳弊社は創業21年。大阪の郊外で現在4店舗の美容室を運営しております。弊社が『理念と経営』共に学ぶ会を始めた理由は2つあります。
1つは、社員さんと会社の価値観の共有。2つ目は異業種から学び、業界の常識に疑問を持てる気づきの多いスタッフに育ってほしかったからです。
この2点に関して『理念と経営』は健全な価値観を育て、価値ある気づきを得ることのできる理想のツールとなりました。
1番成長を感じるのは、社員さんが持ち回りで設問を考え、有意義なディスカッションができるようになり、実際に新しいサービスが生まれていることです。
当初は規定の設問表を埋めて皆でディスカッションをしていました。しかし「もっと実践に落とし込めるような設問表にしたい」という幹部の意見から、幹部が設問表を作るようになりました。それを見ていた社員さんが「皆で作ったら参加意識が高まり、もっと良いものができるのでは?」と意見を言ってくれたことで今の形ができました。
これからも勉強会を通して変化しながら継続していきます。 -
個人の思考を全員で共有し、刺激を受け、成長する会
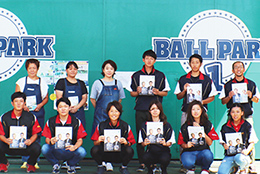
株式会社フィールドフォース
佐藤 祐士弊社は創業13年目を迎える野球用品メーカーです。「プレーヤーの真の力になる」という言葉を経営理念とし、日々の商品開発に励んでいます。
当初は業務に関してのコミュニケーションが多く、刺激という部分では物足りなかったように感じていました。そんな時、ふと思えば、それぞれのスタッフのことに関して互いによく知らないという現状に気づきました。それ以降はスタッフの生い立ちや、現在考えていることを発表する場にもなっています。さらに1人ひとりの経験や考えがわかるにつれて現在行っている業務にも落とし込むことができています。
例えば、商品開発において、各ポジション目線でプレーヤーの気持ちになり、意見を発しています。新規事業としても女子プレーヤーの普及活動などいままでの経験が生きていると感じられるほど、コアなニーズに対応できていると思います。
恥ずかしながら会の締めには私が統括して意見を発表させていただいていますが、いままで考えていなかった視点・可能性を広げていくことを意識して伝えるようにしています。
共に学ぶ会は新しい刺激・観点に触れる場としてこれからも続けていきます。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






