参加者の声
-
多様な個性が集まって起こる化学反応が、この会の醍醐味

竹末 耕三
私たちは、広島市中区にある日創研広島営業所を会場に、毎月開催しています。
年齢、業種はさまざまです。二十歳から七十歳までの、多様な個性がぶつかり合い、毎回、新鮮な討議が行なわれています。
毎号の記事、設問内容に刺激を受け、熱いやり取りが交わされる中で、同じ地域、同じ悩みをもつメンバー同士が意見を語り、的確にアドバイスし合っています。
ベテランは、経験に基づいた深い助言。若手からは、時流に乗った最先端の情報。同じ本を読み、同じ理念をもつ者が集まることで起こる化学反応が、この会の醍醐味です。
私たちの会では、「明日から実践できること」を、出席者に約束していただいています。学んだことは、即実践。まずは小さなことでも、翌日から始めていただく。そのことを、討議の終わりに決意していただくことで、成果を確実に生み出しています。このときの皆様の表情は、本当に輝いています。 この学びを通じて、参加企業の社内勉強会もより良くなるように、今後も取り組んでいきたいです。 -
アドバイスをしたり、いただいたり、自分で気づいたり
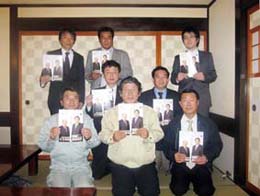
西松 繁夫
北四国地区・愛媛ブロックの一支部を担う私たちは、①必ず開催する、②活発なディスカッションをする、③良い会社づくりに活かすこと、を約束事として開催しております。経営者、経営幹部、幹部社員の皆さんの他、オブザーバーとして社員の方々が参加し、皆さんが集まりやすい昼食時に、ご飯をたべながら活発に議論を展開しています。
時には、設問内容からはみ出したりしますが、「会社をより良くしていく」という皆さんの熱気に包まれて、立場や業種を超えて意見を交換しています。 必ず開催する(長く続ける)、活発なディスカッションをする(出席率が高い、とにかく議論をする)ことは、当たり前のようですが、今振り返ってみると、とても大切なことだと思います。勉強会ではお互いにアドバイスをしたり、いただいたり、自分で気づいたり、解決のヒントが浮かんだり、参加者の皆さんそれぞれで、その相乗効果が現れています。 これからも「良い会社づくり」のために、より価値ある勉強会にしていきたいです。 -
メンバーの絆が深まり活動も活気づいてきた

前本 良人
我が支部は、「沖縄を元気に」する活動をしたいという志をもつ者が、より充実した活動にしていくための勉強会として始まりました。
勉強会を始める前から地域活性化のさまざまなイベントに取り組んでいましたが、メンバーは普通の会社員もいれば個人事業主やパーソナリティーなど多種多様で、一つのイベントを進めようにも、考え方の食い違いなどで衝突し険悪な雰囲気になることも多々ありました。
そんな状況を一変させたのが月刊『理念と経営』の勉強会です。経営者の方々の苦難やそこから得た教訓から、自分たちに足りないものは何なのかを真剣に語りあううちに、当初の熱い想いがよみがえり、メンバーの絆がさらに強まり、活動も活気づいてきました。そして「一緒に笑って心を繋ぐ人脈ネット」を理念に、NPO法人まじゅんの会を設立することができました。
これからも、月刊『理念と経営』を活用しながら、「沖縄の元気のために」何ができるかを考えていきたいです。 -
これほど真剣に勉強できる会は他にはない

今村 斎
私たち昭和支部は、平成十八年の創刊号から六年間、休むことなく毎月一回勉強会を続けてきました。最初は六人でスタートした勉強会ですが、今では一五人まで増え楽しく毎月勉強しています。
全員が異業種の経営者で、①お客様に心酔客となっていただき事業を継続していくこと、②事業を通して従業員の満足と社会貢献していくこと、③会社の継承をしっかり行なうことをポイントに学んでいます。
社長力では「会社はトップの器以上に良くはならない」と言っています。社長にそんな苦言を言う社員は一人もいません。だから真剣に討議ができると思います。
参加者の中には、今までいろいろな会に参加してきたがこれほど真剣に勉強できる会は他にはないと絶賛し、業績が最近上がってきているという報告もあります。
その後は馴染みの居酒屋で、お酒を酌み交わしながらビジョンや夢を語り合い盛り上がっています。今後は経営について学びたいと言う若手経営者を増やしていきたいと思っています。 -
仲間からの一言で苦しみが希望に変わり、明日への活力に

炭田 恵崇
私たちの支部は、「共に学び、共に栄える」ことを目的に、参加者の志の実現と、より高い社会貢献を目指して、2009年4月から毎月一回、賑やかに開催しています。逆境を耐え忍び、社会の変化にすばやく適応して、幾多の困難を乗り越えて、それぞれの理想を成し遂げていこうと頑張っています。
設問表をもとに、各自自由に発表をしていただいた後、自社に置き換えて会社が抱える問題を明確にし、他のメンバーが顧客の立場に立って"お客様目線"を第一にしながら意見交換をしています。
メンバーからのアドバイスによって、自分だけでは決して気づくことができなかったことに気づけるようになるので学びが深くなり、その過程を通して、よりよい戦略や戦術のアイデアに繋がることもあります。
理想と現実のギャップに悩み苦しんでいたことが、仲間からの一言で期待や希望に変わり、明日への活力になる! そんな勉強会を実践しています。
今後も参加者の増益経営のサポートができるようにしていきたいです。 -
新たな気づきを経営に活かし「増収増益」に繋げる

斉藤 博志
私たちの支部では、1.本誌をもとに地域の経営者同士でディスカッションし、新たな気づきを得ること、2.その気づきを自社の経営に活かして「増収増益」経営に繋げることを目的に、経営者の会を実施しています。 毎回、開会にあたっては、次のような言葉を参加者の皆さんと唱和しています。
郷友賦
一、吾等、郷土につながる縁に依り、道に志す朋友どちここに集ひたり。
一、吾等、相扶け共に手を携えて、眞に人たる道を目標とせん。
一、吾等、人生は是 誠の信条に基づき終生學ぶを忘るる勿れ。
この勉強会を通じて、皆さんとのネットワークを築くことができたことは私にとって貴重な財産となりました。私は人材派遣事業を営んでいますが、仕事に有益な情報交換ができるのはもちろんのこと、そのほか経営上の悩みを相談したり、将来の夢や希望を語り合ったりすることができる、大変有意義な時間です。ここで得た学びを会社に持ち帰って、社内勉強会の取り組みにも活かしています。 -
言われてとても嬉しかった参加メンバーからの感想

工藤 哲男
我々の支部は、みんなで学んで刺激し合い、経営者としての人間力を高めるために勉強を続けてきました。
今年に入って「参加人数を増やしグループの分封を推進しよう」という機運が高まり、日創研旭川経営研究会の水野会長を中心に「経営研究会のなかで勉強会を取り入れ、二つの会を活性化させよう」と計画を練り直しました。会員のみならず「広く大きな"輪"をつくって、個人の資質を向上させる」ことを目指して、いま経営者・経営幹部に呼び掛けています。
「こんな意見だと恥ずかしいなぁ」とおっしゃる方もいましたが、メンバーから自由な発言を引き出そうとするリーダーの、適切かつ迅速に進行する姿をご覧になって、「会社の会議・打ち合わせも、このようにやればスムーズになるんですね」と驚いたご様子で、すべてを受容することの大切さを実感されていました。
以前、初参加の方から、「異業種の方からいろいろな意見が聞けてためになる」と言われたことがとても嬉しく、今後も価値ある学びの会として取り組んでいきたいです。 -
「判断基準が間違っていないか」を確認できる、貴重な時間
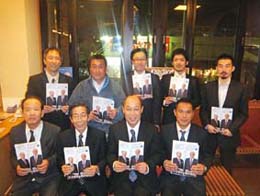
村田 保
わたしたちの東山支部は、発足して今年で六年目になります。毎月欠かさず開催し、毎回十数名の経営者や幹部が集まり、設問表に沿って、熱い議論が交わされています。現在でも新しく参加されるメンバーが増えており、その方々との交流も新鮮で、毎回楽しさの中にも、新しい気づきと、深い学びがあります。
特に二年前からは、議論の前に30分間のプレゼンテーションを設け、メンバーが会社の状況や、悩み、目標、創業の想い、将来のビジョンなどを発表し、質問やアドバイスなどをしています。このプログラムを取り入れたことで、メンバー同士の相互理解が深まり、固い絆を築くことができ、参加意欲の向上に役立っています。
自分だけの視点で物事を判断するのではなく、異業種の方々の意見を率直に聞け、「自分の判断基準が間違っていないか」などを確認できる貴重な時間です。一人で問題を抱え苦しんでおられる方には、ぜひ参加していただきたい。
これからも、自己成長と会社の発展のために、共に学び続けていきます。 -
自社の一押し商品を持ち寄り、お客様視点で真剣な話し合いが...

世良 洋介
愛媛での経営者の会の活動は、大野栄一社長と真鍋明社長と白木秀典社長と西松繁夫専務、若城博之社長の魅力ある経営者のもとに、五つの支部からスタートしました。皆さんに若者支部長を育成していただいたお陰で、今では県内に経営者や経営幹部さんで構成された会が一七支部(一六九名)に増えました。
世良支部では一一名で活動していて、近年は若手有望経営者も多く参加するようになりました。ファシリテ―ションCDを聞きながら設問表を使って討議した後に、自社の一押し商品を持ち寄って、お客様視点で会員同士が話し合ったり、自社の成長課題・問題点を持ち回りで発表し、皆で真剣に討議しています。新人経営者も、よき経営者と人生の親友づくりができています。
会員一人ひとりが「この勉強会にいてよかった」「また参加したい」と思える企画・運営を全員で心がけています。経営者としての考え方が学べ、業績向上にも直結していますし、「努力の継続」を価値観にもった経営者にとっては、大変実りある勉強会です。 -
悩みや課題をアドバイスし合い、多くの気づきを得られると好評

髙瀬 誠
本誌の創刊当初から、神奈川県内で多くの「経営者の会」が活動していましたが、「経営者の会」神奈川地区大会開催後に、県内の仲間から「共に学ぼう」という機運が高まり、神奈川での経営研究会設立に向けて積極的に取り組んできました。
設立準備で一時活動を休止していた横浜の経営者の会でしたが、本年1月から、新たに「神奈川中央支部」と改称して活動を再開しました。経営研究会の毎月の例会で、全国の経営者仲間や各界の著名人から貴重な情報を得ることができるのですが、限られた時間のなかでは自社の悩みや課題を仲間と共有しきれなかったためです。
そこで、我が支部では、自社の経営について定期的にアウトプットし、アドバイスし合える場をつくることを心掛けています。参加者からは「自社や自分の考え方について、多くの気づきとヒントを得ることができる」と好評です。
読者の方なら経営者に限らず、経営幹部の方、独立志望者の方でも参加できるオープンな支部です。近隣の方はぜひ一度、ご参加ください。









![0120-519-114 [受付時間]平日9:00~18:00](/themes/assets/img/common/sp-contact-tel.png)






